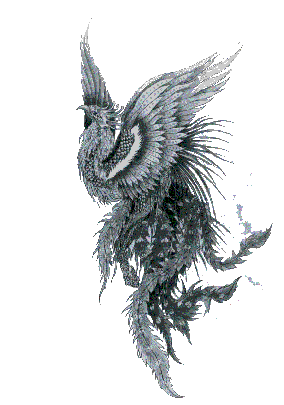| 劇団RAKUYU 第8回公演
紀州歴史ドラマ第二弾
〜悲劇の皇子〜 「アリマ」
2010年11月13日、14日に御坊市民文化会館にて上演
されました。
|
|
『悠久古墳の地を有して』
(現地御坊市にて)
舞台劇「アリマ」上演に際して、有間皇子が埋葬されている説のある市内岩内、「岩内1号墳」の土地所有者、
東京在住でメディア在職の山田(筆名)が、調査当時のことや有間皇子への思いを新聞寄稿。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
岩内に所有する地に「皇室に関わる古墳と解析が出た!公園として保全 へ」と一報を受けたのが、30余年前。
皇室後継の立場で唯一埋葬先が不明だった有間皇子、岩内1号墳は、その形状石室造営法や漆喰の棺、
副葬品等々から終末期古墳において皇位に相当する被葬者として他類なきと皇子の名が上がった一報でした。
多くの古墳群を抱えた「塚野」と称された場で、土地で暮らしながら、旧来大きな石があるというのみの伝承でしたが、
地元史跡研究の巽三郎さんの史料を元に検証された森浩一同志社大教授がこの解析に至りました。
中大兄皇子との後継争いの謀反に命を絶たれたという定説は周知されていながらも、紀州のどの地に埋葬されたかが
長らく不詳。
森先生の顕彰で、このような終末期古墳における立派な石室形状は豪族ではなく皇室後継の立場に在する者であ
り、埋葬の漆喰棺は奈良、大阪以外で唯一の出土、全国においても杞憂な例。考古学は固有名の明言が難しいとされ
るなか、こうして有間皇子の名が揚げられるに至ったのです。
ようやく日の目をみた有間皇子、文化財指定として整備され、その後には、地元での記念祭事が当初に行われ、
初演となった舞台劇「有間皇子」も松本こうじさん演出により実施されました。
ところが年を経て記念行事はなくなり、果ては「有間皇子」の古墳の存在の認識も希薄になる現状に至りました。
平城京遷都1300年に沸く年度を迎え、その律令の時代を前に没した有間皇子を忘れてはならず、唯一皇子の
痕跡を石室古墳として有していることを、もっと重責に唱えるべきと感じました。
私にできることを思った時、この古墳を含め、界隈を有する場を抱えて、何か有意義な発信できる設営をと思ったのが本年。
悠久の地に培われた史実は、癒しの空間や芸術創意工夫、さまざまな英知を発するエネルギーを有していると思いました。
私は今秋、文化財指定以来の敬意を込めて森浩一先生を訪ね、「考古学は地域に勇気を与える」という一言に出遭うことが
できました。
それは、その有史が抱えるエネルギーはそこへ帰属する民の機運を高める勇気だと感じました。
生来、古墳を含めた塚野界隈に在し、所有した縁を大切に、今後の有意義な発信を考えていきたいと思っています。
RAKUYU松本さんが「ふるさとの物語を取り上げることに意義がある」と称され『アリマ』上演に至りますこと、
有意義な発信と感銘。今後一層のご活躍のほどをお祈り申し上げます。
・・・・・・・・・・・・・・・・ 2010年11月9日(火)付 日高新報に掲載
|
|
|